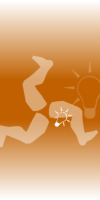 |
堆肥化実験プロジェクト活動紹介堆肥化実験プロジェクトは、東京大学キャンパス内で発生する大量の落ち葉を効率よく堆肥化しキャンパス内で循環させようというプロジェクトです。環境三四郎のメンバー約10名を中心に地方自治体、地域の方々や大学とも協力して活動を行っています。 きっかけ
駒場キャンパス内にある矢内原公園の一角を学部から借り受け、落ち葉を集めてきて堆肥にするという実験が始まり、以来今年まで、8回の実験が行われてきました。 目標まずは、東京大学駒場キャンパスから出る落ち葉の「全堆肥化」を目標とし、毎年効率のよい落ち葉堆肥化へ向けた実験を行っています。最終的にはこの活動がどんどん広がっていき、全国で落ち葉の処理に困っている方々への助けにもなれればと思っています。 今年度の実験
(1)生ごみ堆肥の混入落ち葉堆肥の成熟を早める目的で、生ごみを1次発酵させたものを落ち葉堆肥に加える実験をしました。生ごみを入れなかったものと比べて温度上昇、見た目ともにかなり早く堆肥化が進行するという結果が得られました。 (2)切り返し回数の変化落ち葉堆肥を作る際には、中の菌に酸素を供給する目的で定期的に落ち葉の山を混ぜる「切り返し」という作業が必要です。落ち葉堆肥づくりに重要な切り返しですがこれが割と重労働で、規模を拡大していくためには切り返しの省力化が欠かせません。今年度は従来の半分の切り返し(月1回)を試してみました。 (3)落ち葉粉砕&タヒロンバッグ堆肥化前の落ち葉を粉砕して、成熟具合が変わるかどうかを調べました。 こちらはボックスに積むのではなくタヒロンバッグという1m^3ぐらいの袋に詰め込み冬から実験を行っています。 中学校での環境教育
駒場祭
今後の展望来年度も、「落ち葉全堆肥化」の目標に向けすでに1年生が実験を始めようとしています。地域の人たちとや大学、自治体とのつながりもたくさんできてきて、このプロジェクトに対するニーズも増えてきています。最終目標である全堆肥化や全国への普及へはまだまだ乗り越えなければならない困難がたくさんあると思いますが、着実に一歩を踏み出し始めていると思います。 文責:後藤祐平(15期) |